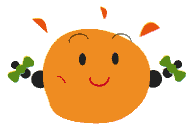 「純子の見聞録」元気ネットワーク98年10月〜12月
「純子の見聞録」元気ネットワーク98年10月〜12月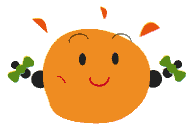 「純子の見聞録」元気ネットワーク98年10月〜12月
「純子の見聞録」元気ネットワーク98年10月〜12月
98.10月号
公的介護保険の実施が本格的になってきました。公的介護保険で大きな役割を果たすことになる介護保険専門員の初めての試験が、9月20日全国19の都道府県で実施され、予想をはるかに越える受験者数であった事が大きく報道されていました。国は公的介護保険がスタートする2000年までに約4万人の介護支援専門員を養成する予定になっていますが、今年の受験志願者は全国で23万人、長崎県においては3265人が受験したそうです。着々と公的介護保険スタートの準備が進められていますが、それに比べて市民の関心はどうなのだろうと大変危惧を抱いています。
今、佐世保市では介護保険事業計画の根拠となる実態調査が実施されています。現在、実際に何らかの介護サービスを施設や在宅で受けているすべての方の実態調査と、また住民基本台帳から無作為に抽出した65歳以上の一般高齢者、及び40〜65歳の一般市民を対象とする利用意向調査です。もう既に調査に答えられた方もあるかと思います。約一万二千人にも及ぶこの調査から介護保険スタートの2000年から向こう5年間のサービスの見込み量を割り出し、その数値を目標として、わが街の介護保険事業計画が策定されます。ですから、この調査が今後のわが街の介護サービスの基盤整備、そしてわが街の介護保険料を決定する際の重要な根拠となるものなのです。
調査は対象者によって、郵送によるものや、民生委員あるいは保健婦・看護婦等の訪問によるものですが、はたしてこの調査の趣旨が充分伝えられているものか、また保険で提供されるサービスが、どんな時に必要なサービスなのか充分知らされないまま答えられた方もおられるのではないかと恐れています。
議会でも再三、市民への広報を訴えて来ました。会期中の今9月定例会に公的介護保険関連の議案が多数出されていますが、その中に様々な広報費用が計上されました。市長自ら地域で説明会を開催する計画も上げられています。またこれも訴えてきた事ですが、介護保険事業計画策定に市民参加が約束されました。公募による参加です。多くの市民に関心を持って頂きたいと思っています。どうか一人でも多く応募して下さい。真の地方分権とはあらゆる意味で程遠い制度ですが、住民自治の一歩として、住民自らが選び、決定していくべき課題だと思っています。保険料とサービスは当然比例しますが、保険料を高く設定するとそれに比例して、国・県の支援が得られます。そこが自治体間格差が生じてくる所以となっています。頑張れば頑張っただけ支援するという仕組みになっているのです。これは市民の合意なしには進めない問題ですが、私は頑張るべきだと考えています。
どこでもお伺い致します。ぜひご意見をお聞かせ下さい。来年の7月頃には事業者・施設の指定が始まる予定ですし、10月には要介護認定作業が始まります。2000年は間近かです。
11月10日、倉島問題で基地特別委員会と全員協議会が開催される予定になっています。倉島問題については、建物の老朽化に伴い早急な対策が必要になった事を理由に8月、市長より議会へ移転断念の方向で打診があっています。
倉島問題とは、さかのぼること昭和60年、海自針尾弾薬庫の建設に際して市有地譲渡の要請があり、その見返りとして出された3項目の要望の一つです。
言うまでもなく、佐世保港は臨港地区および海域のそのほとんどが日米の軍事基地で占められています。佐世保市にとって、せめてその東側を商港として活用するための倉島の集約は佐世保市民の悲願であり、昭和47年の決議以来、再三陳情が繰り返されています。
見返りとしての3項目とは、一つに当時の基地返還6項目のうちの立神岸壁と前畑弾薬庫の一部返還、2つ目に住民・漁民対策事業、3つ目がジュリエット・ベースンの埋め立てとそこへの倉島移転です。しかし完全に履行されたのは2つ目だけで、倉島問題は当初から受け入れられないと表明されていたとか、いないとか先輩議員の見解が分かれていてはっきりしません。しかし、その後この問題の解決のための三者協議会(防衛施設庁・海上自衛隊・佐世保市)が設置されたということは論議の余地があったと考えられます。現在まで6回の協議会と14回の幹事会が開催されたということですが、私には論議の成果が見えてきません。そしてその間、針尾弾薬庫は昭和60年から予算措置され、平成8年度末までに16棟が整備されています。
いったいこの協議会は何だったのか。この10年余り何が論議されてきたのか知るために私は会議録をみたいと当局に申しいれましたが、見せてもらえませんでした。市長は移転断念に際して、議会とも充分話し合いたいと提案しました。いつも不思議に思うのですが、同じ土俵で論議ができるのは、同じだけの情報を共有して初めて成り立つことです。これでは1期目の議員の私には話しになりません。まったく民主的ではありません。倉島問題以前にこのような行政のあり方に問題を感じています。今、私は情報公開条例に基づき会議録の開示を求めています。しかしこの協議会は当初から非公開の合意で始まったとのことで公開の決定が遅れています。佐世保市の情報公開度はどの程度なのか着目して下さい。
10日の基地特別委員会と全員協議会では、論議は尽くされたとして、市長の最終的な判断が示されることになると思います。倉島地区の佐世保市港湾計画は市長見解のように、現在の状況には合わないのかもしれません。しかしもっと先を見たとき、そこに恒久的に基地機能が存続する事は問題です。アジアに顔を向けた都市をめざすのではなかったのですか?
この元気ネットワークの紙面をお借りして、3年あまり毎月、その折々に感じたことや思ったことを書かせて頂きました。毎月となると狭い紙面でも、文章を書くのが苦手な私にとってはおっくうになり、いつ止めようかと幾度となく思ったものです。
しかし改めて読み返してみると、これまでの自分自身の混乱がよく見えてきます。また混乱の中、私のこだわりはただ一点であることも改めて認識させられます。それは地方議会議員として、地方自治の本旨に基づく住民自治、団体自治の確立にあり、それには情報公開と住民参加が重要であるということです。議員としての私も含めた住民意識の改革から始めなければ、この閉塞した政治や行政の状況は打開出来ないと思っています。おそらく、こんな初歩的な事については大方の先輩議員あるいは行政職員はお気づきのことでしょう。今の国と地方の関係の中で、具体的にどう実践出来るのかに努力されてこられた方々にとっては、大変失礼な話だと思います。
これまで私は様々な政策決定過程において、情報公開と住民参加の重要性を訴えていますが、その困難さも同時に実感させられています。
先日、以前報告した佐世保市都市計画マスタープラン策定協議会が開催されました。この協議会は構成委員の決定で非公開になっていますが、私は議員ということで、どういう訳か傍聴が許されています。前にも書きましたが、都市計画法の改正により住民参加を基本に、各自治体がこれから20年間の街づくり計画を策定しています。私はこの経過を追っていく中でもまた、住民参加の難しさを実感させられています。この協議会の会長、副会長は有識者ということで、市外在住の都市計画の専門家である大学教授、助教授が担当されていますが、その他の委員は市内在住の、それぞれの団体を代表する市民で構成されています。論議はなかなか噛み合わないまま時間が経過していきます。市民はそれぞれの思いを発言しますが、行政当局は本音の苦悩や行政執行の手法を、弁解と取られる事を恐れてか語りません。時に本音が出てはくるのですが、双方の事情を良く知る有識者は、時間内の論議はこれが限界とばかりに、上手に会議をまとめ上げます。これではなかなか民主主義の学校にはなり得ず、どこが問題なのか、その解決策をどうすれば良いのか、全体で確認しつつ、論議するところまで進みません。こんな手法で形式的な住民参加としている実態については、誰もが改革の必要性は認めています。でも変わらないのは、「民主主義には時間とお金がかかる」という問題です。しかし、これまで通り財政上の合理性だけを考えていては、市民の意識改革はいつまでも進みませんし、住民自治は確立しません。
これからますます重要性を増してくる地域福祉、共生社会の確立、そして環境問題は自治なくしては考えられません。そしてさらに住民参加のコーディネーターとして、行政職員の役割はますます重要になってくると考えます。今回の都市計画マスタープラン策定においては、様々な住民参加の手法が試みられています。アンケート調査、住民ワークショップ、まちづくり一言提言、インターネット情報等々です。情報提供が市民に分かり易いものかどうかも含めて、市民の関心が少しでも広がることを期待しています。
98-12-8|HOME|