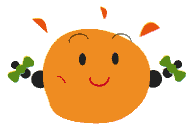 「純子の見聞録」元気ネットワーク99年1月〜3月
「純子の見聞録」元気ネットワーク99年1月〜3月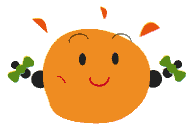 「純子の見聞録」元気ネットワーク99年1月〜3月
「純子の見聞録」元気ネットワーク99年1月〜3月
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い致します。
長丁場の12月議会がやっと終わったと思ったら、少し油断したようで風邪をひいてしまいました。佐世保市では12月議会会期中に前年度の一般会計と特別会計の決算委員会も同時開催され、いつもより長い会期となるのが通例です。おかしな事と思っているのですが、10年度も終わろうかとする時に、9年度の決算を審議する事になります。厳密には前年度の反省が次の年に生かされません。財務会計処理上この時期になってしまう事から、来年度からコンピューター化される予定です。それでも9月議会には間に合わないだろうという事です。システムの完成度もあるのか、9月に間に合っている所もあるようです。
ところで、今回の一般質問の1つに廃棄物問題を取り上げました。佐世保市の一般廃棄物の収集量は平成6年まで減少していましたが、一転増加に転じ毎年増え続けてます。一般廃棄物は家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられますが、佐世保市の事業系一般廃棄物についは、その分別・資源化の実態が殆ど把握されていません。廃棄物の量は経済活動と密接に関係していますが、バブル後の景気低迷に反比例して、殊に事業系ごみは平成6年に比較して、約1・5倍と急激な伸びを示し、バブル期のそれを超えています。このような状況から、今回の質問は事業系一般廃棄物の減量化・資源化に焦点を絞って質しました。
増加の要因として、当局はオフィスオートメーション用紙やプラスチック製のごみが増加している事、あるいはリサイクル経路におけるダンボール、紙類のミスマッチ、つまり需要のだぶつき、また昨今の環境問題の高まりにより、自家焼却を中止したりしている実態があり、その結果、市の焼却施設に持ち込まれているのであろうと考えているとの答弁でした。佐世保市の一般廃棄物の収集量は年間約10万t、その約半分が事業系ごみです。廃棄物処理法によって「事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない」となっています。本市は以前は直営でその収集運搬をやっていましたが、行財政改革において民間の許可業者に収集運搬が委託が出来るようになっています。しかし、委託によってまたその管理責任が生じてくる訳ですが、その対応は十分ではありません。許可業者によって近隣自治体の事業系廃棄物が、本市の焼却施設に持ち込まれている実態があるようで、殊にプラスチック類だという事ですから問題です。また政令で指定された産業廃棄物は特定の業者が排出したという規定で木くず・紙くず・繊維くず等、一般廃棄物と見分けが付かないものも含まれます。これが市の焼却施設に運び込まれている事も考えられます。ぜひとも実態把握が必要だと思っています。
そして、事業系ごみの減量化・資源化への協力要請を強化すべきだと考えます。
本市のごみ処理原価は年間約30億円、事業系一般廃棄物の処理手数料は年間約1億円です。明らかに増え続ける事業系廃棄物をこのまま放置しておく訳にはいきません。市長はダイオキシン対策には最善を尽くすと明言されていますが、あくまで基本はごみの減量・リサイクルです。そこに力点を置いた政策を持って戴きたいと思います。
先般、長崎県下の自治体職員の集会に参加しました。テーマは地方分権・公的介護保険制度・廃棄物行政を中心に広域行政について考えるというものです。私は人口24万人の政令市である佐世保市にあって、頭では理解していたつもりでしたが、県下の自治体、殊に町村レベルの実態についてほとんど分かっていなかった事を痛感しています。1期目の4年間、体験的に規制緩和、民間活力の導入の流れの中で福祉サービスが基礎自治体毎に格差が生じる可能性がある事、あるいは廃棄物・環境問題が現に基礎自治体を越えている実態を知り、必然として広域行政や市町村合併があり得る事を意識し始めていました。しかし、佐世保市の議員という枠に止まり、長崎県の中の佐世保市を本当には、みていなかったことに気付かされています。
まったなしの公的介護保険は、今年10月から要介護認定が始まります。おおかたの自治体の対応は遅れ、要介護認定事業を受託しない方針の長崎県の指導もあって、基礎自治体は広域行政をばたばたと模索しています。ちなみに佐世保市は単独市での介護保険事業を目指し、私もその事に努力して来たつもりですし、首長の意気込みもそうでしたが、ここにきてそうはいかない状況になってきています。また廃棄物行政においては、ダイオキシン類の規制強化への対応も近々に迫っており、平成9年に出された厚生省課長通知によって、県は今年度末までに廃棄物行政広域化計画を国へ提出する予定になっています。
ご存じのように長崎県の人口は153万人。(市部97万人、郡部56万人)中核市である人口45万人の長崎市を筆頭に人口1000人足らずの高島町まで8市70町1村から構成されています。近年急激に人口の増加をみている長崎市近郊の長与町は人口3万8000人、時津町は2万8000人と松浦市の2万2000人を越えています。全国的には、人口300万を越える政令指定都市から200人足らずの村までが存在します。国の財政調整機能にかげりが見えてきた現在、地方分権の進行とともに財政の問題ばかりでなく、人材の面でも小さな自治体ほど深刻な状況である事を今回の集会で改めて認識させられました。
しかしこのまま、なし崩し的に否応なく広域行政が進行していっていいものだろうか疑問に思います。基礎自治体の適正規模を決定する要因は何なのでしょうか。財政の効率性を重視するあまり、地方自治の原点を忘れては元も子もありません。市民の自治意識が失われてはならないと思いますし、市町村の創造的魅力的な自治が可能なものでなければならないと考えています。各論を論議する猶予はないとばかりに広域行政が進行している現状を見るとき、今一度市民の皆さんにその事を問い直す時間さえも残されていないように思えてきます。
はたして自治省の思惑通りに平成の市町村大合併は成功するでしょうか。
3月1日より3月定例議会が開催されます。今議会が私にとって1期目の最後の議会となります。ご存知のように今年は統一自治体選挙の年、改選期を迎えます。議会と選挙、それにこれまで続けてきた地域活動とがあいまって、慌ただしい毎日で原稿締め切り日ぎりぎりになり、編集の方には大変ご迷惑をお掛けしています。
この4年間を振り返って、海のものとも山のものとも分からない私の1期目の当選は、当然のことながら私の可能性、将来性に賭けて頂いたと改めて痛感しています。申し訳ない事にこの世界の事が殆ど分かってなかった私にとって、恥ずかしながら毎日が勉強、勉強。これまでの人生にない新しい発見の連続で、この4年間は私にとって大変充実したものとなりました。最初は何をどう勉強して良いのかさえも分からず、焦りを感じたものです。幸いにも自分自身の公約に沿った委員会に所属する事が出来、関わる事の出来た問題から出来る限り自分のものにしていこうと決意しました。総務委員会、文教厚生委員会、基地対策特別委員会、清掃に関する審議会、青少年問題協議会、保健・医療・福祉審議会、議会運営委員会、これらが所管する問題、財政が分からないと全体が見えないと毎年参加した地方財政セミナー、女性問題等など、手当たり次第といったところでしたが、その内にそれらが繋がってくる事に喜びを感じたものです。殊に力を入れた老人保健福祉計画に始まる公的介護保険制度の問題は、その制度を知るためにもと思って受験した介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修を受ける資格試験に合格。思わぬ御褒美でした。
徐々に総合的に見えてきた地方自治のあり方は、私に議会活動だけに止まっていてはいけない事を気づかせてくれました。そして精一杯、市民の皆さんとの取り組みにチャレンジしてきました。参議院議員の福島瑞穂さんが最近書いておられるのですが、自分自身の活動を分類して、個人でやる事、政党としてやる事、超党派でやる事、市民との強いネットワークでやる事、そのすべてをやる。また違う視点で、主観的に頑張る事、客観的に頑張る事、頑張っているように見える(情報を発信する)事の3つを満たさなければいけないとも書いておられます。国政と地方政治とでは違う点もありますが、これまで私が右往左往取り組んできた事への回答があるように思っています。
今回、私は2期目の挑戦を決意しています。地域住民に身近な課題はもっとも身近な基礎自治体で解決するという地方分権の中で、本来の地方議会の役割を発揮する時代となり、益々重要性を増してきます。そのために今一番大切にしたいと考えている事は、市民の皆さんと情報を共有する事であり、結果だけでなく、結果までのプロセスを明らかにする事だと思っています。市民の皆さんにとって辛い選択でも、その選択までのプロセスの透明性が確保されるなら、理解が得られると信じています。尽きる事のない課題にこれからも精一杯、市民の皆さんとともに頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。
99-3-8|HOME|