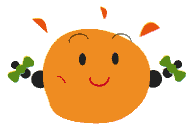
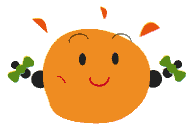
「純子の見聞録」元気ネットワーク97年7月〜12月
<7月号>
ただいま6月定例会の会期中です。私の一般質問と、所属する文教厚生委員会の審議も終了し、最終本会議を残すだけとなり少しほっとしているところですが、市民ネットワークの原稿の締切日はすでに過ぎて、慌てて書いています。
今回の私の質問は
1)公的介護保険創設をにらんだ本市の対応について
2)開かれた学校、教育委員会について
3)本市において今策定中の都市計画マスタープランについて
ともう1点でした。今回の質問の趣旨は少し違っていますが、共通した点でひどくこだわっている自分自身に改めて気付かされている事があります。
1)について、公的介護保険法案は今国会では成立せず継続審議となりましたが、秋の臨時議会において成立するものと思われます。各自治体が保険の運営の主体になり、住民は保険料を徴収されることになるのですが、果たして佐世保市は施行までの3年足らずの間に介護メニューの質と量をどの程度確保出来るのか?市民には殆ど現状を知らされていません。これから被保険者である市民の意見を反映させながら各市町村が介護保険事業計画を定めなければならない事になるかと思いますが、その時、現状を知らされていない市民には、にわかに意見を言えるものでは有りません。介護保険の仕組みと市長の考え方、佐世保市の現状と課題について広報すべきです。
2)について、教育委員会の定例会は本市では月1回行われています。この委員会は原則公開なのですが、佐世保市教育委員会傍聴人規則が昭和27年に定められて以来、過去1回も傍聴人があったことがないという事です。教育長の話では権利は条例によって確保されているので問題はないとの事ですが、全く不親切です。いちいち市民が第1火曜日と定められた条例の条文に精通しているわけではないし、その日の議題も分かりません。東京都中野区のように事前の広報をして欲しい。
3)について、平成5年の都市計画法の改正にともない、各市町村が独自の創意工夫で総合的な街づくりプランを住民参加で策定しなければならなくなったため、佐世保市では平成8年から10年までの3年がかりで進んでいます。実際には都市計画にかかる許認可の権限は市町村にはなく、現行では絵に書いた餅になる可能性は大きいと思いますが、最近出された中央都市計画審議会で権限委譲が答申されています。そうなってくると、このマスタープランを生きたものに出来る可能性は大きいと言えます。
策定の基本は住民参加であること、また地域特性をふまえて地域別構想を策定する事から各地区住民による地区協議会が作られようとしています。この地区協議会が策定後も地域に息づいて、地域の総合的街づくりのノウハウを蓄積していく地域に密着した組織体に出来ないものか。
以上、指摘しました。つまり、私のこだわりは地方自治の基本である住民自治は情報を住民と共有するところから始まる事。そして住民自治を重視すればするほど、民主的な政治や行政が営まれてくるということではないでしょうか。
最近、長崎大学教育学部の舟越教授の講義を聴く機会がありました。御自身のライフワ―クとしてドイツのワイマ―ル期・ナチス期の法哲学・法思想の研究をされています。第一次世界大戦後の反省から生まれた理想的ともいえるワイマ―ル憲法下で、なぜヒトラ―の専制政治が罷り通り、そして再び二度目の大戦を引き起こしたのか、その時の法哲学者達はどの様に考えたのかが主な講義の内容でした。その根底には太平洋戦争の反省から生まれた日本の平和憲法が日米防衛協力のガイドライン見直しにより歪められていく可能性がある現在の状況への警告があったのではないかと思われます。
ここで、憲法問題に触れるべきなのでしょうが、その講義中、論議になったヒトラ―時代の法に因んで「悪法も法なり」あるいは「法は法なり」という法哲学の命題としては古くて新しい命題に及んだ時、私はまったく違う問題を考えていました。「元気ネットワ―ク」にも連載されている白岳町の産業廃棄物の中間処理施設の問題です。
廃棄物の問題はこれまで私なりに問題意識をもって考えて来ました。学習も、してきたつもりですが、現状を知れば知るほど、限り無く消費を促す資本主義経済の限界を思い知らされ、環境破壊による被害者が同時に加害者である構図が見えてきます。その中で資源循環型の社会をいかに創造していくべきかが問題になり、またその事は一国だけの課題ではなく、地球に住む人類全体で取り組むべき課題である事に気付かされます。環境問題は
「地球規模で考え、行動は身近な事から」
という合言葉に行き着きます。そしてその事を市民の皆さんと一緒に考え、行動したいと望んでいました。
白岳町の産廃中間処理施設の問題が浮上してきた時、私は廃棄物問題を真剣に考える住民がおられた事を喜び、佐世保市のゴミ事情を共有するために市内のゴミ処理施設の見学ツア―を企画しました。行政の一般廃棄物処理施設、市民から目隠しの状態にある山中の産業廃棄物の処理施設を見て回る中で、日本の廃棄物処理の法整備の杜撰さを含めて理解して戴き、自分自身の生活を見直していくところから運動を始めたいと思っていました。 しかし、白岳町の周辺の住民の皆さんにとっては、リサイクル社会が構築されるまで待てるものではなかったのです。当然の事ながら起こった住民反対運動の経過はこの紙面ですでに皆さんは御存知の通りです。この問題は住民が行政訴訟を起こす、あるいは事業者が行政訴訟を起こすということになるのでしょうか。裁判となればどちらにしても市民の税金が投入される事になります。住民反対運動が国の法整備を早急に促す手段である事も確かな事なのかも知れません。当事者ではないからだとお叱りを受けるかも知れませんが、現にある廃棄物の山を目の前にして、あるいは中央政府と地方政府の関係の現状からして、今と違った形の反対運動があるような気がしてなりません。
また、最初の命題「悪法も法なり」に戻りますが、自然法的思考からすると悪法と正しい法という価値判断があり、時、所を越えた絶対的正義、実定法を越えるあるべき法があるとするならば、それに従うべきであり、私の取っている態度は間違っていると言えます。
地方議会における議会運営委員会の設置は平成3年、正式に地方自治法第百九条の二に追加明記されたのだそうです。議会制民主主義が理想的に実現されるような議会運営の有り方を審議し、決定する機関ということです。
当初、何も知らず何処の議会も同じなのだろうと思っていました。その内あちこちの自治体議員さんにお知り合いが出来てくるとどうも話が噛み合わない。そこで初めていろんなやり方があるのだという事に気付きました。4月の当初予算だけは全員の議員で審議する特別委員会を設置するところ、各常任委員会の日程をずらして当該委員以外でもその審議を傍聴出来るようにしているところ、会派交付金と言われる調査研究費の交付のしかたや額がまちまちであること等々です。
今回、私は2年毎の委員の交代で初めて議会運営委員になり、今の佐世保市の有り方がなぜそうなっているのか、どのような議会運営がベストなのか、自分自身改めて整理しなければならないという新たな課題が私に与えられました。そこで1回目の委員会において類似都市の議会運営について視察したいと提案し受け入れられ、2班に分かれて合計6市の視察に出掛ける事になりました。
本市における課題はいろいろあるようですが、当面している課題について視察のポイントを限定しようという事になりました。その課題の1つは「議案質疑と一般質問の区別」です。その会期に提出された議案にたいして事実関係だけを確認するという議案質疑にどうも議員の所見を述べるウエイトが強過ぎているようです。この事は私も厳密に区別出来るものではないと思っています。質疑の意図を明確にするために議員の考え方を示さなければ答弁に齟齬が生じてきます。先輩議員の質疑のやり方を聞いていると相当なテクニックがいるようです。現に視察の結果はほとんどが区別せず、本会議ではまったくやっていないか、あるいは一般質問に組み込まれた形になっていました。議案質疑が提出された議案そのものと、また議会での審議過程も含めて市民への情報提供という役割を果たすものなら、それが本会議でなされるものなのか、付託された常任委員会でなされるものなのか、市民の「知る権利」を行使するスタンスにも大いに関係して来ます。
次に取り上げられた課題は上記の事と関連するのですが「委員会の会議録の情報公開」です。情報開示請求があって少し揉めた事があって視察のテーマになりました。
本会議は全文が記録に残りますが、委員会の記録は要点記録になっていることから恣意的要素が強いということで、開示の対象になっていなかったようです。しかし、当然全文筆記、また個人のプライバシーに係わる問題を除いて全面公開の方向で考える事は明白であり、そのための条件整備が問題になります。視察先でも当然基本的な考え方は一致しています。そして、本市に比較してその条件整備に努力されているところが多かったように思いますが、1つ感じたことは、どこもご多分にもれず情報開示請求がほとんどないし、委員会の傍聴もほとんどないというところが多く、緊急の必要性を感じておられないように思えた事です。ここでも市民の「知る権利」の行使が問題のようです。もう1点感じた事は本市における情報公開条例はいち早く制定されたのですが、一般市長部局と議会はそれぞれに別に条例を制定しています。視察した自治体全部が1つの条例に組み込まれていました。紙面の都合で次の機会にしますがここにも問題があるように思いました。
長崎県議会に提出された請願と同様の趣旨の「中学校歴史教科書の記述に関する請願書」が佐世保市議会9月定例会に提出されました。そしてまたその請願とは相反する趣旨の請願が市内の女性を中心とする33の団体から連名で提出されました。その審議は私が所属する文教厚生委員会に付託されます。
慰安婦問題について軍の関与を政府が認めた事もあって、今年から検定歴史教科書に僅かではありますが記載されるようになり、この種の請願が地方議会に提出されるようになりました。佐世保市議会においても先の6月議会にいったん提出されようとしましたが結局取り下げられた経緯もあり、いずれ論議は避けられないものと思っていましたので、少しずつ関連の書物に目を通したり、学習会に参加したりしていました。その争点は強制の捉え方がそれぞれ違っていること、戦争下においては他の国でもやっていた事を敢えて自虐的に書く必要はないというものと他がやっているからいいというのはおかしいというもの、そして、教える時期が問題だとするものがあるようです。また明白な論議は避けられていますが、外交問題があり、個人レベルの国家賠償が浮上する事への恐れがあるように思います。
勿論、歴史教科書に記載されるべきものは歴史的事実でなければならない事は言うまでも有りません。えてして自国に都合のいい歴史認識で教科書は作られ勝ちですが、より客観的事実に基づいた歴史教科書であるべきですし、それが自国にとって辛く苦しい歴史であっても、意図的に削除すべきではないと考えます。
それぞれの請願者による趣旨説明は当然ながら、その双方が自分たちの言い分が歴史的事実なのだと主張していました。双方の主張で少なくとも、
1)多くの慰安婦が軍の移動とともに移動した事。
2)軍が直接多くの慰安所を設置し管理した事実がある事。
3)日本人の慰安婦と植民地あるいは侵略地の慰安婦の処遇が違っていた事。
これらは歴史的事実として認めています。戦争下あるいは植民地下においてまた貧困下においてNOといえる状況でなかった事は強制のなにものでもないと私は思っています。
明日、佐世保市文教厚生委員会としての結論を出さなければなりません。果たして一地方議会に歴史教科書の内容を審議し、真実が何処にあるのか実証する能力があるとは思えません。また一方で政治が教育に介入すべきではないという論議があります。民主的方法で教育内容を決定するシステムにおいては政治の介入はあり得ると思いますが、その内容事態に介入する事はあってはならない事であるとも思っています。本当に気の重い審議になりそうです。
市民には請願法により請願権が保障されています。地方議会にも毎定例会に多くの請願や陳情が提出されます。その多くが国への意見書提出を求めるものが殆どです。請願はどんな内容であってもいい訳ですが地方議会に直接裁量がある地域に密着したものは少ない事を疑問に思います。国政に係わる問題は直接国会請願をしてはどうでしょうか。
<11月号>
先頃「高齢社会をよくする女性の会」第16回全国大会が北九州市において開催され、参加しました。小倉市民会館を埋めた全国から集まった女性のパワーに圧倒され、又励まされもした2日間でした。日本の高齢化の速度は世界的にも例がない急速なものである事は御存知の通りです。そして、女性にその介護の負担の多くが課せられている現状も現実です。この会は結成以来、女性と介護に視点を当てながら、介護要求の増大は社会問題であり国民全体で支えるべきものとして、介護の社会化を進める運動を続けています。
全国に広がる会員の機動力を駆使して様々な独自の調査をされていますが、今回は介護表彰を実施している全国自治体の調査結果をおもしろ可笑しく寸劇にして報告されました。端的にいうとその実態は介護嫁表彰であり、良き嫁であらねばならないという思いと介護の肉体的にも精神的にも、そして金銭的にも厳しい現実の狭間で泣いたり、笑ったり、怒ったりしながらただただ頑張っている嫁の置かれている現状を知るに付け、「喜劇は悲劇に通ずる」という思いを強くさせられる寸劇でした。
調査は新潟県を除く46都道府県で実施され、結果、市町村3120のうち31・3%が何らかの形で介護表彰を実施しており、改めて介護が家族に大きく依存したものになっている実態が明らかになりました。同時に介護が嫁や娘に担わされ、それを行政が気持ちばかりの品物と「嫁の鏡」と褒め称える表彰状を贈る事により、介護者がますます女性に固定化し、逃れられないでいる実態も浮き彫りになりました。これは明らかに高齢者福祉における行政の怠慢でしかない事を強く実感させられました。忍耐強く控え目な日本人が「介護は自己責任で解決すべき個人的問題である。家庭内の問題は他人に手助けしてもらうべき問題ではない。また嫁が女性が頑張らねば誰が頑張るんだ」という呪縛から完全に解放されるのはいつの日でしょうか。先ずはその呪縛から解放されないかぎり、今、論議されている公的介護保険制度は中途半端なものにしかならず、介護の社会化は実現しません。
この会の次の取り組みとして「家族介護の実態調査」が予定されています。10年前にも同様な調査が実施されていますが、10年経過した今、どのくらい意識の変化があったのか、またどのくらい介護の社会化が進んだのか調査しようというものです。佐世保市内の介護家族にもアンケート実施協力をお願いしてみました。応じて戴けた女性のおおかたが無記名にも係わらず、親類や地域の人に知られる事への恐れ、また行政への不満を言う事への恐れがあって本音で書けないと言われた事には大変驚かされています。その一方では、自分自身が介護を必要とするようになった時、その介護者を尋ねる質問には「施設に入りたい」と答えています。その時入れる施設があるでしょうか。この現実をみんなの問題として真剣に考える時は今です。何とかなるとなどと思わないで下さい。
この全国アンケートの調査結果は来年出ます。またお知らせしたいと思っています。
6月議会開催中に全員協議会において新大学問題が唐突にも市長より提案されました。9月議会の全員協議会にも設置主体の学校法人九州文化学園からの説明とともに、より具体的な提案がなされました。すでに市民の皆さんは新聞紙上でその詳細については御存知の事と思います。
総事業費は約60億円、設置場所への進入道路建設費用を加えると60億円を超える事業に多くの県・市の公的資金(うち市の助成額38億円)が投入される事の是非についての論議が沸騰しています。議会としては所管する総務委員会を中心にすでに調査が始まり、9月議会には多くの先輩議員の一般質問がなされています。正式な議案として議会に上程されていない以上、まだやるともやらないとも市当局の意志が市民に表明された訳でもないのに、具体的な論議がなされていく事に不思議さを感じています。
議会の議決を要する事項は地方自治法96条に規定されていますが、その13の事項はあくまでも制限列挙であって、重要と思われる案件については予算化される以前に議会に正式に提案し、市民の前に明らかにすべきではないかと思っています。議員になって2年半が経過しましたが、議会運営の有り方が見えない自分自身に気付かされています。
9月議会での一般質問の内容は多岐に及ぶものでした。その殆どが大学設置に対しては歓迎するものの、38億円という市民の税金が一私学に投入される事への疑問だったように思います。これからますます財源不足が予想される状況の中でなぜ今なのか。他の政策課題への影響は。無理を承知でやるメリットは。九文・県・市の負担割合はどの様にして決定したのか。市の助成金の調達方法は。これからの少子化傾向の中で設置後の学校経営は大丈夫なのか。教授陣の確保は?文部省の許認可は得られるのか。西九州道路矢岳インターとの関係は。ハウステンボスとの関係は。県立大学の総合化との関係は。文教地区との関係は。等々です。そのひとつひとつにほとんどよどみなく市長答弁がなされました。しかしよどみがあろうとなかろうと不安は払拭出来た訳ではありません。
ある架空のお話です。750万円の年収がある家庭です。家族が多いためそれでは遣り繰りが出来ません。80万〜100万円程、毎年借金をしてどうにかやっていけています。借金を繰り返したので今では借金の合計は750万円程になってしまいました。これから先も長男の大学進学、長女の結婚、曾祖父の100歳のお祝い、雨漏りがしている自宅の屋根の葺き替えと出費が次から次に控えています。借金が膨らんできているので毎年のローンの支払いもここ数年徐々に増えてきていて、近い将来年100万円以上返さなくてはならなくなってしまいます。御存知のように食費は嵩むし、子どもの教育費やおばあちゃんの入院費それにローンの支払い等必ずいる費用は年700万円ちかくになっています。貯金も少しは持っていたのですが、それも徐々に減って現在70万円足らずになっているでしょうか。これでは何か急にあった時の事を考えるととても不安です。
そんな状況で貴方だったら、将来に夢をかける38万円を何とか捻出できますか。
97-12-26/98-1-3 |HOME|