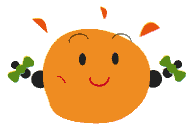 「純子の見聞録」元気ネットワーク98年1月〜9月
「純子の見聞録」元気ネットワーク98年1月〜9月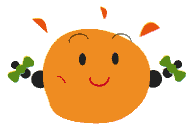 「純子の見聞録」元気ネットワーク98年1月〜9月
「純子の見聞録」元気ネットワーク98年1月〜9月
<1月号>
明けまして、おめでとうございます。
年末も押し詰まって慌ただしくこの原稿を書いています。議員になって二年半が経過し、少しではありますが議会の仕組みが理解出来てくると、現職の議員が後々に残される文章を書き続ける事の難しさを感じ、なかなか筆が進みません。出来るだけ本音で書きたいと思いつつ、結果的には経過報告になってしまっている気がしています。そんな事柄ならマスコミ報道の方がよっぽど正確です。私が書き続ける意味を明確に持つべきなのでしょう。どこまで書けるものか、いつまで書き続けられるか分かりませんが、今年もどうぞよろしくお願い致します。
今回は9月定例会において「継続審査」になっていた「中学校歴史教科書の記述に関する請願」の12月定例会の結果を報告致します。「継続」とはいうものの、閉会中に一度も委員会審議は開かれませんでした。前回、水面下の意見調整についてある議員から、議会制民主主義において有るまじき行為であり、正面きって議会の中で論議すべきであるとの批判がありました。私も当然そうあるべきだと思っています。どのような請願内容であろうと議員の能力の範囲において議論し、結論を出さなければなりません。結局は多数決の論理で結論が出される事になります。
現在の文教厚生委員会の会派構成は自民2、緑政2、民社1、公明1、市政1、社民1になっています。改定を求める請願の紹介議員は緑政と民社で、それに反対する請願の紹介議員は社民です。前回は公明から継続動議が出されました。微妙なバランスの中で結果が予測出来ないまま12月議会に臨みました。結局私に出来る事は、自分自身の考えるところを誠実に訴える事しかない、結果的にこの請願を阻止出来なかったとしても、精一杯やれることをやるしかないと私は思っていました。多数決の論理において破れる事も含めて、市民が選挙で選んだ結果なのだから仕方のないことです。
しかし、12月議会を終えた今、市民のパワーに何か明るい手応えを感じています。改定に反対する請願をした女性たちが今回の委員会審議過程を傍聴に来てくれた事が、微妙に委員会のムードを変えたように感じるからです。結果はまたもや「継続」となりましたが、確実に委員の皆さんの考えの変化を感じています。傍聴が市民の政治参加の一つの方法として、こんなに効果のあるものなのかと驚いています。選挙だけが政治参加ではないということです。委員会が終わった後、委員の皆さんが口々に、会派内の調整が問題である事を言ってくださいました。次回の審議も予断を許しませんが大いに期待したいところです。今回、傍聴をされた方は審議内容に腹立たしさを感じられた事と思います。継続審議と言いつつも内容に進歩がないと、私自身思うからです。この請願事項が地方議会の論議に馴染まないし、実証能力においても限界があると思いつつ、またもや「継続」という結論で、問題解決を先延ばしにしてしまいました。もしかすると、これが政治というものなのでしょうか。
昨年の暮れ、住民の訴えがあって、私の所属する党の代表を務める県議会議員とともに市内のゴミ事情を視察して回りました。
烏帽子岳に続く木風町の林道沿いは廃棄物の不法投棄のメッカになっていて、ゴミの山が大きくなると不審火が発生し、消防車が出動するとのことです。途中、何ヶ所か黒く焼け焦げた不法投棄の後が残っていました。山中で操業する廃棄物処理業者の不適正処理のためか立ち木の変色が広範にみられ、野焼き同然の操業実態は目に余るものがあり、水質汚濁の危険性も懸念されます。周辺の住民の健康被害への不安と行政への不信は、頂点に達していました。
産業廃棄物行政を直接所管するのは、県の役割となっています。しかし、佐世保市は過去30万を超える人口を有し、単独市で保健所を設置している自治体となっていますので、市長は廃棄物処理に係わる許認可の権限と監督・指導の権限を有しています。
佐世保市では、これからますます重要性を増す保健・福祉及び環境の問題を充実させるため、昨年4月、保健及び福祉の機構改革が行われ、保健福祉部と環境部に改編されました。しかし環境保全全般を直接担当する環境保全課のスタッフは、課長以下数名であり、産業廃棄物に係わる事務から、大気汚染・水質汚染・騒音・振動・放射能・浄化槽の問題等々、自然環境保全にかかわる膨大な業務を担当しています。果たして佐世保市に、産業廃棄物に関して政令市や中核市と同様の役割を果たせる体制があるのか、疑問に思っています。
昨年12月、環境庁は大気汚染防止法施行令を改定し、遅ればせながら初めてダイオキシン類を指定物質に加えました。また厚生省は、廃棄物処理法施行令・施行規則を改定。焼却施設の構造基準及び維持管理基準を見直すほか、小規模施設に対する規制強化のため、許可対象範囲の見直しや野焼き防止のための処理基準を明確化。併せて、ミニ処分場に対する規制を強化するため、最終処分場の裾切りを撤廃。また産業廃棄物管理票制度を、これまでの特定産業廃棄物からすべての産業廃棄物に適用範囲を拡大する等々、改定されました。決して充分とは言えませんが、一歩前進だと言えます。
しかし、言うまでもなく、法は生かされて初めて法となります。5年間の段階的経過措置を経て、平成14年からはすべての基準が適用となります。これらの施策の徹底には、環境保全課の果たすべき役割が益々重要となります。そのため、より一層の推進体制充実が求められます。市民の生命を守る行政への期待は大きいと言えます。行財政改革とは時代の行政ニーズに柔軟に対応し、課題のプライオリティを再検討する事だと考えます。
わが党は近々、市への申し入れを予定しています。今日、この原稿を書く前に、要請文の原案に頭をひねっていたところですが、言いたい事ばかりで、まとめるのに一苦労です。
長崎県知事選挙と衆議院長崎県4区補欠選挙が、慌ただしいうちに終わりました。私達が擁立した衆議院議員候補は善戦したものの、小選挙区制度の壁は厚く、残念なことに敗北に終わりました。今回の選挙で「誰がなっても同じだ」とある若者が言いました。そう簡単に諦めないで欲しいと思いつつも、現状の政治や行政のあり方ではそうかもしれない、何も答えられない自分自身を情け無いと思っています。
地方議会の議員になって3年。現在の中央集権的な行政や政治のあり方に大変疑問を感じています。それが政治を見えにくくしているとも思っています。
戦後の新憲法において初めて、第8章に「地方自治」の条項が設けられました。理念としては地方政府と中央政府の対等な関係を規定していると考えますが、実際は理念だけに留まり、旧憲法の中央集権制を大いに引きずり、御存知のように国に権限が集中しています。その事が政治腐敗の根源であり、すべての自治体がそうだとは言いませんが、お任せ的な元気のない地方になっているとも言えます。
権限や財源の範囲内で工夫を凝らし、頑張っている自治体もありますが、財源的に恵まれない多くの自治体は、国が揃えた事業メニューに従って政策を決定し、そのメニューが地域の課題に多少合わなくても、やることによって国や県の補助金が地域に落ちる事を選択せざるを得ない現状があります。そしてその事業には必ず市町村の負担金も伴う事になりますから、僅かに残された貴重な単独財源をそこに当てたり、あるいは借金をしてその財源を確保したりしなければなりません。その前段で国や県への陳情費用も用意しなければなりません。そうなると、益々財政は硬直化してきます。
昭和50年代の前半から「地方の時代」と言われてきましたが、ここにきてようやく1995年、5年間の時限立法として地方分権推進法が成立しました。それに基づき設置された地方分権推進委員会はこれまで4次にわたる勧告を内閣総理大臣に提出しました。今後のスケジュールとしては、政府部内での分権推進計画づくりと地方自治法全面改正作業が進められ、今通常国会に提案されることになっています。その後、総合的かつ計画的に地方分権推進に取り組んでいく事になりますが、この事を憲法理念にそってしっかりやり遂げる事こそが、見える政治、クリーンな政治に繋がっていくと考えています。そして今が正念場であるとも思っています。生活に密着した地域の課題への、責任を伴う地域住民の自己決定権、これこそが地方自治だと考えますし、その事を担保する地方政府であって欲しいと思っています。中央政府の役割は広域的、全国的、国際的課題に整理されるべきでしょう。
今回の衆議院補欠選挙に私達が擁立した候補は、中央に大きなパイプを持っている人ではありません。しかし、地方をよく知る人であるからこそ、中央の政治・行政がよく見える人であると言え、地方分権推進の課題に積極的発言の出来る人でした。先ずは貧しくとも一歩前進したいものだと思っています。本当に残念な敗北でした。
官官接待、カラ出張など公金の不正使用が明らかになる中で、国の情報公開法案が審議過程にあり、情報公開を求める市民の気運は徐々にではありますが高まっています。だからという訳ではありませんが、佐世保市議会においても議員自ら襟を正し、審議過程や議会費について公開を原則とするための見直しが、議会運営委員会において論議の過程にあります。
1つは委員会毎に予算化される視察費の問題です。これまで調査視察費と行政視察費に分かれていた予算を行政視察旅費として一本化し、減額する見直しです。調査視察と行政視察の定義に明確な違いがなく、調査視察費には緊急な課題への行政視察の予備費的な意味合いがあったようです。また本当に必要な視察であったのか、予算があるから消化するという事では許されないという反省があったようです。当然、一本化したとしても議員のモラルの問題が解決する訳ではありません。だから、新しく策定された「常任委員会視察実施要領」に「緊急な調査等の発生を予測して消化するものとする」という文言が入れられる事になりました。論議の途中、この文言を入れる事が私としては、何だか恥ずかしい事のように思えました。予算とは目的を達成するため、最小の費用で最大の効果を生むよう努力して立てられるものと思っています。もし緊急かつ重要な課題が年度途中で発生すれば当然補正予算を組んで対応しなければなりません。議会とはそのチェックが役割であると言えますが、その議会で必要だから予算化した視察費を当然残すべきという条項を設けることを論議するのは、何だかおかしいと思い、その事を発言しました。が、予算消化のための視察の問題が長い間論議されてきた経過があったようで、他の委員の間には「何を今更蒸し返すのか」という白けたムードが流れ、聞き入れられませんでした。因みに、今回決定した議員一人当たりの委員会行政視察旅費は年30万円です。併せて、海外視察の規定についても来期より見直す予定になっています。
2つ目は第二の議員報酬と言われている「市政調査研究費」会派交付金の問題です。この事もあちこちの議会で問題になっています。その使途については規定がありますが、再度曖昧な部分を明確にする審議過程にあります。当然、収支報告書あるいは視察報告書の提出は義務付けられています。議会運営委員会の視察で訪れたある自治体の会派交付金は、一人あたり月十数万円という所もありました。自治体の規模によって随分違いがあるようです。佐世保市は5万円となっています。誤解があるといけませんので付け加えますが、あくまでも議員個人に交付される訳ではありません。
3つ目に、委員会会議録の全面公開に向けた作業に入っていることがあげられます。今年度の議会費に各委員会の録音機器の整備予算が計上されました。これまでの要点記録をより全文記録に近いものにするためのものです。しかし「佐世保市議会委員会条例」の改正が未だ成されていないために、当然、関連する委員会傍聴の規定の改定がなされていません。そのため、本日行われた文教厚生委員会の傍聴希望者は委員会の公開制限を楯に傍聴を許されませんでした。改正作業を急がなければなりません。
議員自らが、開かれた議会に向けて努力しなければなりません。また市民も、自分自身の税金の使途や議会の審議過程の情報公開を求めては如何でしょうか。
消費者運動の始まりは、顔の見えない商取引の時代に入ってからと言われています。大量生産・大量販売・大量消費・大量廃棄の各段階において、様々な問題が引き起こされて来ました。結果、消費者運動の高まりとともに、生産者と消費者が対等の関係ではなく、消費者は保護されるべき弱い存在であるとして、消費者利益の擁護推進を目的とする消費者保護基本法が、昭和43年に制定されました。本格的消費者保護行政の始まりです。そして、今年は制定30周年の年にあたります。
ところで、佐世保市に消費者運動の母体である生活学校が10ある事を御存知でしょうか。佐世保の生活学校運動の歴史は古く、昭和38年に始まります。多くの先輩達によって地道に続けられてきた消費者運動も、今ではメンバーの高齢化に伴い、その活動も低迷した状況にあります。私の所属する生活学校もご多分に漏れず、同様の状況にあります。しかし、私たちを取り巻く消費生活は、より複雑化、多様化し、消費者問題は、「たくあんから放射能まで」と言われるように、取り引き上の問題から地球環境の問題までと広範囲です。また望む望まないは別として、規制緩和の大きな流れの中で、消費者の自己責任がますます問われる時代になり、消費者運動の重要性はより増してきている状況と言えます。消費者運動は、人が人として安心して暮らせるための生活者運動であり、その意味で、これまでの主婦だけの運動ではなく、若者や男性も大いに関心を持たなければならない課題と言えます。
私たちの生活学校は、一念発起し、今年「高齢化問題」に取り組みました。その一貫として、3月、ドキュメント映画「住民が選択した町の福祉」(演出:羽田澄子)の上映会を企画しました。多くの皆さんのご協力で、盛会のうちに終了する事が出来ました。またメンバー一人一人が、主体的に運動に係わる事の意味を、少しだけでも実感出来た事は、大きな成果であったと思っています。
消費者運動の一貫として企画した理由は、昨年末に成立した「公的介護保険法」で、介護サービスが市場原理の下に提供されることになり、2000年から自由競争の時代に入るためです。メディカル・コンシューマー(医療消費者)としての権利意識が確立しているアメリカに比べ、わが国においては制度の違いもあり、医療サービスを購入しているという意識は薄く、サービスの中身を知るという権利意識も薄い状況にあります。このような状況の中で、介護保険で提供されるサービスを経済取引上の消費財やサービスと捉える事が出来るかどうか、多少疑問であり、無理があるようにも思います。しかし、まだまだ不確かな介護保険制度を自ら自由に選び取るものにしていきたいと願っていますし、それに足るサービスの量と質が確保されたものにしていかなければならない、と願っての取り組みでした。
いろいろな意味で、弱い立場にある高齢者を食い物にするような、悪質な業者の参入を決して許さないという「賢い消費者」の目を、今から持つ必要があると思っています。
5月臨時議会は2日間の会期日程で開催されました。議案は、長崎国際大学(仮称)開学支援補助金拠出のための一般会計補正予算案と、昭和55年に創設された観光会館設立基金廃止のための佐世保市基金条例一部改正案の2件です。この経過については、すでに報道も多くなされていて、1日の会期延長の末、賛成多数で可決成立したことも含め、よく御存知の事と思います。
以前、この紙面でもお伝えしましたが、昨年6月、全員協議会において唐突に議員に説明があって以来、いずれは議員として結論を出さなければならないこの問題について、私は土壇場まで迷い続けていました。私が所属する会派の意向に反した結論を出す事についても、表決の土壇場まで迷い続けていました。そして迷った挙げ句、反対の結論を出しました。
その後、ある私の支持組織の方から、義務として反対の理由を明確にすべきである事を指摘されました。それは当然の事だと思います。不可解な点について議案質疑はしたものの、表決の際に反対討論をしなかったのは、フェアではないとも思っています。この紙面を借りて、説明させて戴きたいと思います。紙面の都合で細かい所までお伝え出来ませんので、もし希望があれば、説明に伺いたいとも思っています。
当初私は、議会の正式の場で論議されない事にこだわると同時に、何故一私学に多額の公的資金が投入されるのか、他の多くのわが市が抱える行政課題を差し置いて、何故優先されるのか、大変疑問に思いました。結果的に反対した理由は、このすべての疑問が西九州自動車道路の4工区(干尽町〜矢岳町)の都市計画決定に係わる、九州文化学園の移転と関係があるとしか思えなかったからです。財政支援を約束する県と市が交した覚書の内容や、短期間に水面下で進められた経過あるいは県の用地課の担当者の発言等からの判断です。この事が関係が有るのか無いのか、市長の答弁は当然明確なものではありませんでしたし、4年生大学設立と九文の移転問題は無関係との事でした。景気低迷の昨今、契機はどうであれ、大学の有用性は大いにあり、知的刺激は勿論のこと、経済的な波及効果に期待したいという意見があります。将来そのような効果が期待出来るものなのかどうか、市長は調査結果を示しながら、有ると判断しました。議員の多くもそのように判断しました。もしかするとそうなるかもしれません。議案が可決した今は、貴重な税金を無駄にしないためにも、市民全体で素晴らしいものにしていかなければと私も思っています。
しかし、この事は高度な政治判断であると、どなたかがおっしゃいましたが、不透明な部分を許しながらやってきたこれまでの政治に、市民は嫌気がさし、政治離れが進んだのではなかったのですか。情報公開の大切さが叫ばれているのではなかったのですか。いつまでこのようなやり方を続けるのでしょうか。私は疑問の一石を投じたいと思いました。
道路をつくるために、公共の福祉の名の下、長年住み慣れた人々は辛い移転という権利侵害を余儀無くされます。犠牲を強いられる九文と高等教育の場を確保したいという佐世保市の意向が重なり、発展的に4年制大学創設が論議され、市民との合意が形成されたとしたなら、どんなに良かったかと私は思っています。
6月定例会も最後の本会議を残すのみとなりました。今回の私の一般質問は、お年寄り・障害者・子供たちの問題、そして佐世保市の廃棄物行政とダイオキシン類排出規制の問題の4点です。いつもの事ですが、折角苦労してまとめた質問も、質問テクニックの未熟さから、思うような答弁を引き出す事が出来ず、残念に思っています。
今回の質問の狙いは、5月の臨時議会で可決した新大学への助成金を大いに意識し「私たちの佐世保市はこんなにも生活関連の課題を抱えているんですよ。」という事をアピールする事にありました。ポートルネッサンス21計画を含む駅周辺の再開発事業は、好むと好まざるは別にして、すでにスタートしています。この事は別にしても、私たちの生活に密着した多くの福祉や環境の緊急課題があります。
私はこれまで自分の公約である福祉について、ずっとこだわりながらやってきましたが、ある方から「福祉、福祉というけれどね・・・」と言われました。暗にもういいんじゃないのというニュアンスだったように思います。この市民の意識に代表されるように、これからの福祉の方向性は民間活力の導入という言葉に象徴される規制緩和の流れと、それに付随する自己責任に置き換えられようとしています。その事を皆さんが分かったうえでの発言だったのだろうかと思いましたし、私のこれまでやってきた事はこの規制緩和の流れの中で行政責任の範囲を明確にする作業であった事を、皆さんに私自身伝えきれてない事にも気付かされました。公平性や透明性が確保され、安心して暮らすことが出来るためには、今の財政状況や経済状況をも現実的にとらえ、最大限可能な行政責任の範囲はどこなのかを求める。そこのせめぎ合いこそが政治なのだと改めて思っています。
そして今、福祉は一定市場経済に乗せられようとしていますし、環境破壊の問題はこの市場原理には馴染みにくい問題だったからこそ、大きな社会問題を生んできました。
「神の見えざる手」に委ねられる世界は純粋モデルであって、最低公共が果たす役割としてルールをつくったとしても、完全なルールは有り得ないし、そのような窮屈な社会は御免被りたい。自由競争の中で安くて、便利なものをつくった者が勝ちという事では、環境問題は解決しません。その事が廃棄物行政に大きなツケを残してきました。佐世保市のこれから10年の長期財政計画に乗せなければならない廃棄物関連課題の財政出動は、年間の一般会計予算に匹敵する額になる可能性があり、この事を憂慮した今回の質問でした。
また、今年3月策定された佐世保市エンジェルプランは少子化対策の計画ですが、今回はその中の学童保育について整備促進の方法を質しました。これもまったく市場経済に委ねようとしている答弁で、再質問においてやっと非営利団体の育成について触れました。この事を佐世保市の福祉に対する姿勢の象徴のように改めて感じていますし、これからも皆さんと一緒に行政責任の有り方を考えて行きたいと思っています。
最後になりましたが、継続審議になっていた教科書問題は不採択で決着しました。これは市民の皆さんの運動の成果だと思います。そして当該委員であった私がどんなに励まされたか分かりません。本当に有り難うございました。
以前、この紙面で都市計画マスタープランについて書いた事がありますが、覚えていらしゃるでしょうか。わが街の将来ビジョンを決定する都市計画マスタープランは、これまで県レベルで策定されていました。それが、平成5年の都市計画法の改正で、全国すべての市町村において、マスタープランの策定が義務づけられました。佐世保市においても3年計画で約3000万円の策定経費が計上され、今年度中に完了する予定になっています。わが街のマスタープランづくりは、現在地区別構想のための地域住民懇話会で行われている事を、御存知でしょうか。
議員になった当初、私はそこに住む住民の意向を無視した街づくりが、なぜ行われるのか知りたいと無謀にも思いました。それには街づくりの基本法である都市計画法を知らなければと思った訳ですが、調べて行くうちに、密接に関係する法律だけでもざっと60を越え、その他にも建築基準法等の関連法を加えると無数にあることを知りました。都市計画法は税法と並んで複雑で、膨大な法律の双璧をなしているのだそうです。その何処に問題があるのか等という事は、法律家でない私にとって一朝一夕に分かろう筈がなく、またまた議員の仕事は何なのか分からなくなってしまった経緯があります。一つ一つの地域の問題解決が、この法体系を変えていくことに繋がると思いますし、この事をこつこつと粘り強くやっていく事が地方議会の議員の仕事なのかなとも思っています。
そんな時、神奈川県真鶴町の住民参加の街づくりの取り組みについて知る機会がありました。改正法の中でしっかりとうたわれている市民参加の手続きを踏んで作り上げられた街づくり計画は、素人の私にも分かる平易な言葉で書かれたものでした。規制の表現を数量の尺度で捉えようとすると難しい面があり、それを質を表わす文章にする事で容易に街をイメージする事が出来るようになっています。また他の自治体では、住民が自ら策定したわが街のマスタープランを作った所もあります。
私はわが市のマスタープランづくりに、しっかり住民の意志を反映させてほしいと議会で質問しました。その後、都市計画課に行くたびにその進捗状況を伺ったり、策定協議会を欠かさず傍聴したりしました。かなりしつこいと担当職員を悩ませたように思いますが、その甲斐あってか、担当者は自分自身の費用で研修や視察に出掛けられたりと、随分努力されたようです。肝心の住民の参加はというと、広報されてはいますが、思うようにはいっていないようです。私が参加した1回目の相浦地区の地域住民懇話会は動員もあって地域の有識者の参加が目立ち、一般の参加者は少なかったようです。
しかし、ワークショップ形式の話し合いは興味深く、一定成果を上げたと思いますし、私はこれも一歩前進と捉えています。その中で確実に、行政職員も市民も、そして私も学習していると実感しました。これから地方分権が本格的にスタートし、益々住民自治の有り方が問題になってきます。都市計画の権限が市町村に委譲されます。それに先立つ都市計画マスタープランは、将来ビジョンにも匹敵するほどの総合的計画です。
1回目の懇話会は地区を一巡したようですが、まだ2回目の予定が残っています。ぜひ参加して地域の実情や要望を行政に届けて下さい。簡単な事です。こんな産廃施設は迷惑だとか、あの公園はいいとか、この自然景観は大事にしたいとか、この商店街を人の集う所にしたいとか、この道は狭いとか暗いとか、この並木は素晴らしいとか、この川は汚れていて臭いとか、あの建物は外観はいいが使い勝手が悪いとか、下水道の問題とか、言えばきりがないほど有るではありませんか。
8月4〜6日、国立婦人教育会館において 、財団法人市川房枝記念会とニューヨーク市立大学大学院 女性と社会研究センター の共催による「日米女性フォーラム」が開催されました。全国各地から政治参画を真摯に考えようとする多くの女性たちが集まりました。アメリカの現職議員を初めとする活動家との活発な議論を通して、日本の現状とこれからの課題を再認識し、私は元気を得て帰って来ました。
「鹿児島県下の女性議員を100人にする会」が、各都道府県における女性議員在籍自治体の割合を調査しました。つい先ごろ出されたその結果によると、長崎県下79の自治体の内、一人でも女性議員が在籍している自治体は25で、在籍率全国ランキングは46都道府県中39位となっています。まったく女性議員がいない54の議会は当然、男性の物の見方、考え方、価値観で、自治体の意志が決定されていくことになります。全国ランキング44位の鹿児島県で結成されたこの会では、鹿児島県下96の自治体すべてに、まずは一人でも女性議員を出していきたいと考えています。
なぜ今、女性の政治参画が重要なのでしょうか。女性の特性を生かした政治とは、どのような政治なのでしょうか。様々な議論から次のようなことを考えさせられました。「男性と女性に大きな特性の違いはない。これまで男性は経済至上主義の社会システムの中で重要な役割を担ってきた。そして女性は家庭の中の役割を担ってきた。大きなツケを残してきたこれまでの経済システムに組み込まれていない女性だからこそ、しがらみがない女性だからこそ、これから重要とされる生活優先の政治が可能なのではないのか。女性議員が増えることによって、環境・福祉・教育等にもっと光が当たるのではないのか。これまでの政治の手法をなかなか変えられない閉塞した状況を、打開出来るのではないのか。」等々です。現に女性の政治参画率の高い国々は、そのような経過をたどって来ています。
ご存知のように世界的にみても、日本における女性の政治参画率は低く、国会レベル125位、地方議会はそれより低い状況です。日本の地方議会議員の女性の比率は4.6%、アメリカでは現在20%台とのことですが、それまでになる過程には日本と同様の悩みがあった事は言うまでもありません。まず女性の政治参画における障害として、家族の理解が最初に上げられます。殊に夫の理解を得ることが問題であることは自由の国アメリカでも変わりないようです。その他選挙費用の問題など様々な問題がありますが、最大の問題は女性自身の意識改革にあります。日本では「面の皮を厚くする」と言いますが、アメリカでは「ワニの皮」にならなければと、政治参画への勇気を強調されたアメリカの地方議員の発言は、自分自身の体験と重なって、思わず苦笑いしてしまいました。
来年は統一自治体選挙の年です。一人でも多くの女性が勇気あるチャレンジをしてくれることを期待したいと思います。
98-9-18|HOME|