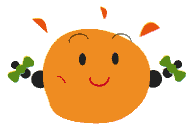
佐世保より4月6日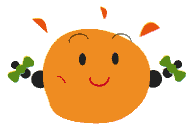
リムピースにアクセスして下さった皆さん、始めまして!
リムピースの趣旨に大いに賛同し、基地のある町佐世保に暮らす住民として、また、市議会議員として仲間に加えて頂きましたが、申し訳ないことにパソコンなるものがほとんど理解出来ていませんでした。
事がすでにスタートしてから特訓です。
時間がないのに加えて、おばさんとしてはすでに頭が固くなっていて大変遅くなってしまいました。また、理解が進むとインターネットによる情報発信の底知れない広がりに今は恐れも感じています。しかし、私がぐずぐずしている間、佐世保の私の仲間は佐世保基地の情報として米艦船の入港状況を掲載し続けています。
私が基地の問題を真剣に考え出したのは、正直言いますと議員になってからの事です。議員としてのテーマを狭義の福祉と環境に置いていますが、基地特別委員会に所属することになり、責任ある発言を求められる事になった時、佐世保の実態をほとんど知らない自分自身に気付かされました。裏を返せば直接基地に関わる事のないかぎり普通の佐世保市民のその多くがその実態を知らないまま暮らしているのではないでしょうか。
昨年7月、女性が米兵に後ろから襲われ喉を掻き切られ重傷を負うという事件が起きました。それに対し女性たちが抗議集会を開いたのですが、沖縄のあの少女レイプ事件の後だったにもかかわらず、はっきり言って盛り上がりに欠けました。自分たちにとっても、いつ降りかかってくるか分からない、共通する問題であることの認識を共有出来なかった事を大変残念に思いました。私有地を含む沖縄本島の20%を占める沖縄の基地、騒音問題かかえる厚木基地等々、目にみえる形で直接日常生活を脅かされる基地とは一種、佐世保基地は違っているように思えます。基地に対するマスコミからの情報は決して少なくありません。にもかかわらず無関心に暮らせるのはその地理的条件にあるように思います。佐世保湾をぐるりと囲む形で基地が存在し、湾自体もその83.1%が制限水域に指定され、市民は自由に使う事が出来ません。陸の方からは基地は目隠し状態にあり、海の方から見たとき初めて基地の存在の大きさを実感します。
ここで少し佐世保市と佐世保港の沿革に触れたいと思います。佐世保港の軍港としての起こりは明治16年にさかのぼります。旧海軍の九州地区の鎮守府設置候補地調査に東郷平八郎を艦長とする軍艦『第二丁卯』を派遣したことに始まります。明治19年、天然の良港に着目され鎮守府設置が正式決定し、明治22年、第3海軍区佐世保鎮守府が開庁しました。当時4千人に過ぎない寒村であった佐世保村は軍港設置後、急速に人口は膨れ上がり、町制を経ないまま一挙に明治35年、市に昇格し、昭和19年には28万人を越える九州第4位の都市となりました。戦後、昭和21年米海軍佐世保基地が創設され、昭和27年日米行政協定により米海軍基地に指定されました。翌28年後の海上自衛隊佐世保地方総監部が設置され、昭和30年陸上自衛隊相浦駐屯地が発足し、佐世保は防衛の拠点となりました。
佐世保川の河口、中州に開けたわずかな平坦地に基地が存在し、住民は傾斜地に、へばりつくように暮らしています。都市がスプロール化するに従って、弾薬庫までわずか160mという危険な状況が生じています。基地問題をかかえる他の町とネットワークを持つことにより、気付かなかった自分自身の町の多くの問題が見えてくるのではないかと1年生議員の私としては期待しています。
どうぞ、これからもよろしく!

|HOME|MISAWA|YOKOTA|ATSUGI|IWAKUNI|SASEBO|OKINAWA|AIR|SEA|SONOTA|'97-4-6