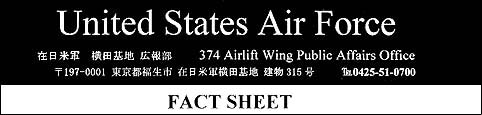
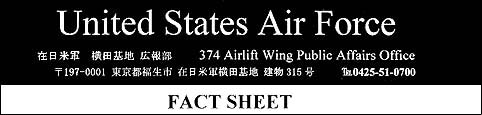
横田基地の歴史(占領時代の始まり)
米軍による占領時代の始まり
 1945年8月日本は戦争に負け無条件に降伏した。連合軍は米軍を中心に日本の占領を進めていった。戦時中、鬼畜米英と教えられ、その言葉さえ使うことを禁じられた日本人にとって、アメリカ人は何をするか分からない存在だった。「男は強制労働に処され、若い女は強姦される」など、様々なデマが飛んだ。1945年9月のことである。その恐るべき鬼畜米英が福生にもやって来た。人々は家の戸を固く閉ざして彼らの様子を伺った。一億総飢餓と呼ばれ、食べるものはもちろん、職も、希望も無い、戦時中より恐ろしかったとされる一時期である。
1945年8月日本は戦争に負け無条件に降伏した。連合軍は米軍を中心に日本の占領を進めていった。戦時中、鬼畜米英と教えられ、その言葉さえ使うことを禁じられた日本人にとって、アメリカ人は何をするか分からない存在だった。「男は強制労働に処され、若い女は強姦される」など、様々なデマが飛んだ。1945年9月のことである。その恐るべき鬼畜米英が福生にもやって来た。人々は家の戸を固く閉ざして彼らの様子を伺った。一億総飢餓と呼ばれ、食べるものはもちろん、職も、希望も無い、戦時中より恐ろしかったとされる一時期である。
恐怖をくつがえした勤労奉仕
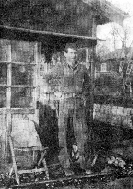 1945年(昭和20年)9月3日、米軍が多摩飛行場に進駐してきた。すぐに基地内清掃等の勤労奉仕の要請が当時の福生町から出された。町は各町会のその割り当てをおこない、日本人らしく一生懸命働くようお願いした。町の人達は初めて見る体の大きなアメリカ兵に恐怖を感じながら勤労奉仕の動員に参加した。実際にアメリカ兵に接してみると意外に明るく、仕事中も案外のんびりしている。休み時間はきちんと休ませるし、過酷な労働もほとんど無かった。これはまったく予想外のことだった。この事はそれまで戦時中に教え込まれて来た「鬼畜米英」などのアメリカ観を根底から覆し、逆にアメリカ兵に対し好意を持つようになっていった。
1945年(昭和20年)9月3日、米軍が多摩飛行場に進駐してきた。すぐに基地内清掃等の勤労奉仕の要請が当時の福生町から出された。町は各町会のその割り当てをおこない、日本人らしく一生懸命働くようお願いした。町の人達は初めて見る体の大きなアメリカ兵に恐怖を感じながら勤労奉仕の動員に参加した。実際にアメリカ兵に接してみると意外に明るく、仕事中も案外のんびりしている。休み時間はきちんと休ませるし、過酷な労働もほとんど無かった。これはまったく予想外のことだった。この事はそれまで戦時中に教え込まれて来た「鬼畜米英」などのアメリカ観を根底から覆し、逆にアメリカ兵に対し好意を持つようになっていった。
日本人労働者第一号
米軍は基地に進駐するとすぐに旧日本軍のボイラーを使用するため、陸軍航空審査部の当時のボイラーマンであった上野秋則に対し、すぐに基地に来るよう出頭命令を出した。その時上野は、アメリカ軍の中へ一人で呼び出されたのだから恐らくこのまま生きてかえれまいと不安を抱き、家族の者と別れの杯を交わし、必死の覚悟でジープに乗せられていった。
ところが仕事が終わってみると、たばこやチョコレート等をくれて、「明日もまた来るように」といわれて帰って来たので、家族のものは泣いて喜んだ。
1940年(昭和15年)日本帝国陸軍立川飛行場の拡張飛行場として多摩陸軍飛行場がつくられた。これが現在の横田基地の前身であるが、当時地元では福生飛行場と呼ばれていた。1939年当時、国道16号線は現在より50メートルほど東を通り、街道の西側はJR青梅線まで桑畑が続き東側一帯は松や雑木の林であった。
多摩陸軍飛行場建設のために、この福生村(1943年町に1970年市になった)の東部一帯の静かな森、雑木林、農地は軍の命令で半ば強制的に買収され、のこぎりや斧により木々は次々と切り倒されていった。予定地内には狐の繁殖施設・養弧園や弓道場など4つの施設があったが、いずれも移転、退去した。
1940年8月15日、飛行場の開場式がおこなわれ、陸軍の花形機・九七式戦闘機3機が飛んだ。滑走路は全長約1200メートル、幅50メートルで、当時としては東洋一の軍用飛行場であり、その大きさと長い滑走路ゆえに新しく作られた最新鋭機の飛行試験を行うには理想的であった。立川から飛行実験部が移転、さらには陸軍航空審査本部を初め、航空整備学校、発動機試験所、気象部などの諸機関が置かれ、1942年終わりまではフル稼働で戦時中の頂点に達していた。1944年4月10日、昭和天皇が飛行場を訪れた。この訪問は当時の航空機技術の視察及び士気を高めるためのものであった。契約センターの南側に残る「甲府岩」はその時の訪問を記念するものである。
当時福生飛行場と呼ばれていたこの空港に戦闘航空部隊が配属されたという記録はないが、様々な使命を帯びたたくさんの航空機がこの飛行場を使用した。第二次世界大戦直後、この飛行場にはおよそ180機以上の航空機があった。
米軍は終戦後13日目の1945年8月28日厚木飛行場に空挺師団の先遣隊を送り込むことにより日本の占領を開始、その後、厚木を拠点として他の軍事施設も同様に占領が進められていった。
米軍は9月8日に多摩飛行場に来る計画でいたが、実際にはそれよりも速い9月3日午後6時、米陸軍一中尉に先導された約20名のアメリカ兵が3台のトラックで、第3ゲート(現在のF86が展示されているロータリー近く)に現れた。
予期せぬ出来事にゲートの憲兵はびっくりした。陸軍航空審査部の有森光夫少将は進駐軍の到着が早かったことに驚いたが、すぐに第3ゲートまでエスコートを送った。当日の業務が終わってすでに一時間以上が経っていた。有森少将は戦前米国で教育を受けており、前司令官・隈部正美中将が自殺した後、基地の指揮を執っていた。
日本帝国陸軍少将と米軍中尉との間で、主に進駐軍のための基地施設再利用計画について会話が交わされたが、この会話の中で米軍中尉は日本が降伏した後、前司令官一家7人が自殺したことを知らされた。
翌日、有森少将は共同航空整備師団の武器庫の責任者・山口少将に電話をかけ、米軍による統制が基地のすべての武器から始まることを伝えた。
日本が戦争に負けた後もなお、多くの日本軍人は武器がある限り降伏しないと決意していた。若い日本人軍人将校の一団は、剣や銃を見せ付けて山口少将を脅し、米軍に抵抗するよう要求した。当時、日本海軍の飛行機が空からちらしを撒き、進駐軍に抵抗するよう勧めていた。しかし、山口少将は進駐軍に協力したため、多摩陸軍飛行場はスムーズに米軍の管轄下に置かれることになった。
1945年9月6日米軍第一機甲師団の分遣隊が到着。本隊の到着まで基地の警備に当たった。第一機甲師団分遣隊のペンジャミン・ヘイス少佐が山口少将より「降伏の剣」を受け取り、この日をもって米軍は公式に多摩飛行場を占領することになった。
9日後、第2戦闘資材群(カーゴ・グループ)が到着。ウィリアム・J・ベル大佐が基地の指揮権を握り、この米軍基地の初代司令官となった。(横田という名称が正式に採用されたのは1946年8月のことで、当時の基地の北東にあった小さな村の名前にちなんで名付けられた。それまでは一般的に進駐軍と呼ばれていた。初代横田基地の司令官は同年B-29の航空機事故で亡くなられたエドウィン・B・ボブジン大佐である。)
1945年9月から1952年4月28日にサンフランシスコ条約が発効されるまでの間、日本はアメリカの全面占領下にあった。
'98-1-18/1-23|HOME|